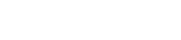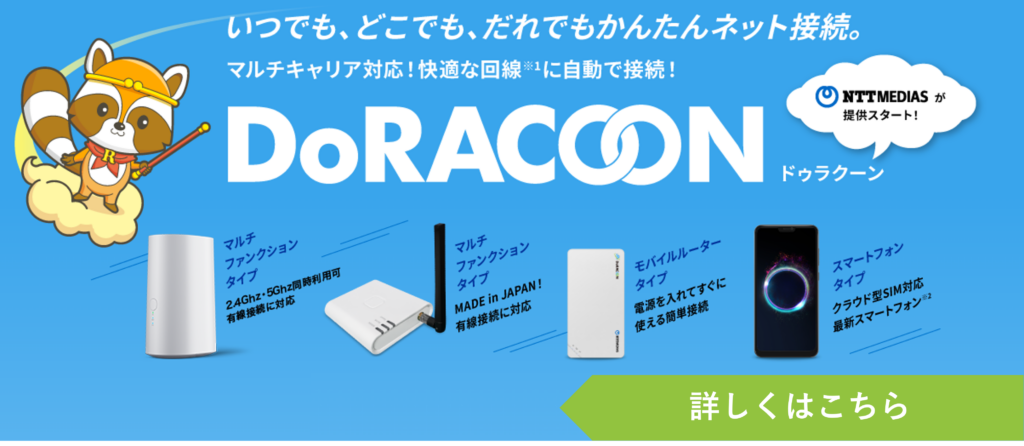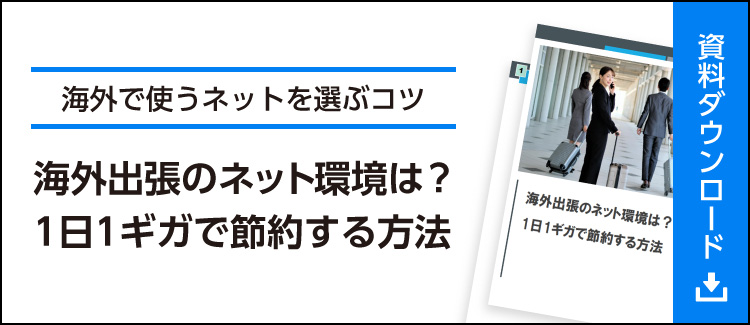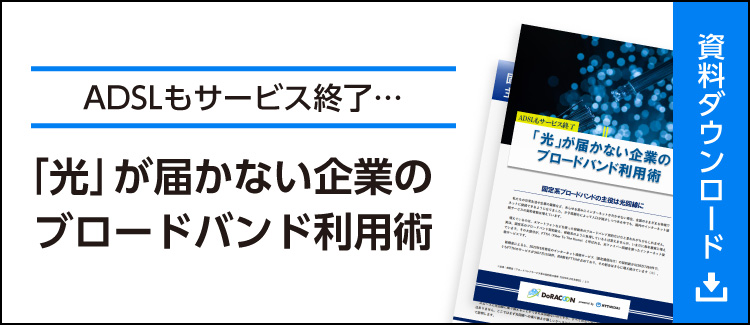有線LANは、ネットワークにおいて安定性と高速な通信を提供する重要な技術です。
本記事では、有線LANの概要から無線LAN(=WiFi)との違い、導入手順までを紹介します。
INDEX
- 1.有線LANの特徴
- 2.有線LANが無線LANよりも高速な理由
- 2.1.送信と受信を同時に行える
- 2.2.他の端末と同時に通信できる
- 2.3.WiFi5以降は1対多で通信できるが同時通信できる端末数は少ない
- 2.4.ケーブル接続だから信号がしっかり届く
- 3.有線LANと無線LANの比較
- 3.1.データの伝送経路
- 3.2.速度
- 3.3.セキュリティ
- 3.4.設置
- 3.5.適しているケース
- 4.有線LANの構成要素
- 4.1.LANケーブル
- 4.2.ルーター
- 4.3.ハブ/スイッチ
- 4.4.LANアダプタ
- 4.5.LANを構成する機器は規格を統一する
- 5.有線LANのメリット
- 5.1.高速にデータ転送できる
- 5.2.セキュリティが向上する
- 5.3.ケーブルをつなぐだけでネットワークを構成できる
- 6.有線LANのデメリット
- 6.1.機器の利用場所に制約がある
- 6.2.ケーブルの敷設コストがかかる
- 7.有線LANのケーブルタイプ
- 7.1.カテゴリ
- 7.2.形状
- 7.3.シールド保護
- 8.有線LANの導入手順
- 8.1.デバイスにLANポートがあるか確認
- 8.2.ルーターや無線APの空きポートを確認
- 8.3.配線ルートを考える
- 8.4.配線作業を行う
- 9.有線LANと無線LANの特性を活かした併用がおすすめ
有線LANの特徴
有線LANは、コンピューターやネットワーク機器にケーブルをつないで構築した局所的なネットワークのことです。
有線LANは、無線LANに比べて高速で電波干渉されることもないうえに、大幅な速度低下が起こることが少ないため安定したデータ通信を提供します。
有線LANが無線LANよりも高速な理由
有線LANが無線LANよりも高速に通信できる理由は、主に次の3つが挙げられます。
- ・送信と受信を同時に行える
- ・他の端末と同時に通信できる
- ・ケーブル接続だから信号がしっかり届く

送信と受信を同時に行える
無線LANは送信と受信のどちらか片方しか行えません。
アクセスポイントと同じ周波数を利用して通信を行うため、送信と受信を同時に行うと信号が衝突してしまうためです。
無線LANは例えると、片道1車線しかない道路のようなもので、
送信が終わったら受信、受信が終わったら送信と、順番待ちの時間が生じます。
一方有線LANは、1本のLANケーブルの中に8本の心線が入っており、送信用と受信用とで使用する伝送路が物理的に分かれています。
上り車線と下り車線が分かれている高速道路のようなもので、同時に送受信しても信号がぶつかりません。
送受信が同時に行えるという点で、有線LANは無線LANよりも通信の効率が良く、スピーディーに通信できます。
他の端末と同時に通信できる
有線LANは、送信時に他の端末が通信していても、それに構わずに信号を送信できる仕組みです。1本の道路上に他の車が走っているときに、自分の車も進入できるイメージです。
同時に接続する端末が増えても、効率的に通信できます。
一方無線LANは、他の端末が通信しているときは送信を待つ必要があります。
送信前に電波を通じて他の機器が通信していないかをチェックし、通信中の端末がなければ送信を開始、通信中の端末があれば通信が終わるのを待つという仕組みです。1本の道路上に他の車が走っているときは自身の車は進入できず、他の車がいないタイミングを見計らって乗り入れるイメージです。
WiFi5以降は1対多で通信できるが同時通信できる端末数は少ない
WiFi5(IEEE 802.11ac)から、MU-MIMO機能により、アクセスポイントが複数の端末と同時通信できるようになりました。
ですが、同時通信できる端末数は最大4台程度(※)です。
MU-MIMOとは、多数のアンテナを搭載することにより、通信経路(ストリーム)を複数持てる機能です。
「1つの道路には車1台しか乗り入れられない」という原則は変わりませんが、その道路の本数が増えるイメージととらえるとよいでしょう。

たとえば、アンテナを4本もつアクセスポイントは、最大4本の道路を持てます。
しかし、最大4本の道路を持てるからといっても、端末4台が同時通信できるとは限りません。
端末側も、複数のアンテナを持つからです。
たとえばiPhone(11以降)はアンテナを2本もっているため、最大4本の道路のうち、2本の道路を使用してしまいます。
1機器あたりのアンテナの最大数は8本となっており、アンテナが2本ある端末を利用する場合、同時通信できる端末は最大4台までに限定されます。
(※)アンテナ8本のアクセスポイントにアンテナ2本の機器が接続する場合
ケーブル接続だから信号がしっかり届く
有線LANは以下の点で、信号がしっかり届き、安定して通信できます。
- ・ケーブルで接続するので遮蔽物の影響を受けない
- ・ノイズが多い場所ではシールド処理されたケーブルを利用することでノイズを防げる
有線LANは端末をケーブルで接続するため、ドアや間仕切り、壁のような遮蔽物の影響を受けません。
無線LANは隣の部屋だと電波は届きにくくなりますが、有線LANはそのような心配がなく安定した通信環境を構築できます。
ただし、外部のノイズによって電気信号の波形が乱れやすくなる点は同じです。
工場などの電磁波ノイズが多い場所では、シールドで保護されたLANケーブルを使用することで、ノイズの影響を抑えられます。
有線LANと無線LANの比較
有線LANと無線LANの違いをまとめると、次のとおりです。

データの伝送経路
有線LANはデータの伝送経路として、物理的なケーブルを利用します。
一方無線LANは物理的なケーブルが不要で、通信に電波を利用します。
速度
一般的に、有線LANのほうが無線LANよりも高速に通信できます。
無線LANは、遮蔽物や同時接続台数、外部からのノイズ等によって通信速度が変わり、環境に大きく左右されます。
セキュリティ
有線LANは物理的なケーブルを利用するため、建物の外から不正アクセスされる心配はいりません。建物に侵入された場合は脆弱になるため、建物内へのアクセスを制限する対策が有効です。
一方無線LANは電波を利用するため建物の外からでもアクセス可能であり、セキュリティリスクが生じます。
第三者にアクセスされないよう、適切な暗号化を施す必要があるでしょう。

設置
有線LANはケーブルの配線が必要なため、設置に手間やコストがかかります。
一方無線LANは、無線アクセスポイントと端末に設定を施すだけで済み、端末台数が少なければ短時間で完了します。
適しているケース
有線LANは高速で安定した接続を求めるときや、セキュリティを重視する場合に適しています。無線LANは、デバイスの移動や配置の自由度を重視するときに適しています。
それぞれの特性に応じて、相互に連携させるのが望ましいでしょう。
有線LANの構成要素
有線LANを構成する機器について解説します。
LANケーブル

LANケーブルは、コンピューターやネットワーク機器を有線で接続するためのケーブルです。
一般的には青色のものが多く、モジュラジャックを少し大きくしたようなプラスチックのコネクタ(RJ-45)が両端についています。
1本のLANケーブルの中には通常8本の心線が入っており、心線間や外部からのノイズを防ぐため、2本一組の撚り線になっています。
ルーター
ルーターはデバイス同士の通信を制御する装置で、ネットワーク構築に欠かせないものです。
LANポートをもったルーターであれば、有線LANを構築できます。
据え置きタイプの(持ち運びできるタイプではない)無線ルーターであれば、標準でいくつかのLANポートをもっているため、有線LAN用のルーターとしても活用できます。
ハブ/スイッチ
ハブとスイッチは、ネットワーク内でデバイス同士を中継するための装置です。有線で接続させたいデバイス数に対しルーターの空きポート数が足りない場合は、ルーターの接続先にハブやスイッチを置くことでポート数を増やせます。
ハブは受け取ったデータをすべてのポートへ転送しますが、スイッチは特定の宛先ポートにのみ流すため、効率的な通信を実現できます。

LANアダプタ
LANアダプタは、LANケーブルを接続するためのインターフェースを提供する装置です。
LANアダプタが内蔵されていないデバイスの場合、LANアダプタを外付けすることで有線LAN接続できるようになります。
USBポートに接続することで有線LAN接続できるようになるアダプタが販売されており、ノートパソコンやスマートフォンに使用されます。
LANを構成する機器は規格を統一する
新たにLANケーブル・ルーター・ハブ/スイッチ・LANアダプタを購入する場合は、対応する通信規格を統一させましょう。
たとえばすべてをギガ対応にすれば、どこかの機器で速度が遅くなることはなく、快適に通信できます。
ハブが100Mbpsまでしか対応しない場合は、ハブ以降のネットワーク通信速度は最大100Mbpsとなり、速度が遅くなってしまいます。
有線LANのメリット
有線LANはケーブルをモデムやルーターに挿すだけのため、無線LAN(WiFi)と比べて設定がしやすく、電波にただ乗りされたり悪用されたりする心配が少なく、セキュリティ面でも安心です。
有線LANのメリットを見ていきましょう。
高速にデータ転送できる

有線LANは一般的に、無線LANよりも高速に通信できます。
送受信を同時に実行でき、通信中の端末があっても自身の送信を待つことがありません。
ケーブルで配線されるため遮蔽物の影響を受けにくく、離れた部屋であっても安定して通信できます。
セキュリティが向上する
有線LANは建物内部に侵入されない限り、不正アクセスされるリスクは低いといえます。
無線LANは適切な処理を施さないと電波を傍受され、通信内容を覗かれるリスクがあります。
ケーブルをつなぐだけでネットワークを構成できる
有線LANはケーブルをつなぐだけで利用でき、設定作業は不要です。
LANケーブルを繋げるだけのため、モデムとパソコンの間に距離があっても、安定的に通信を行うことができ、SSIDやパスワードの管理も不要なので、管理コストを削減できます。
有線LANのデメリット
有線であるがゆえに直射日光にさらされる環境下や部屋のレイアウトなどで、ケーブルの劣化が進み、中の導線に影響が生じると通信障害がおこることがあります。
有線LANのデメリットについても触れていきます。
機器の利用場所に制約がある
有線LANにおけるデバイスの利用場所は、ケーブルが届く範囲に限定されます。
デバイスを移動して使いたい場合には向きません。
ケーブルの敷設コストがかかる
ケーブルを敷設するためのコストがかかります。
規模が大きい場合は、業者に依頼する必要があるでしょう。
配線をきれいに目隠しする場合は、モール等の部材も必要になります。
またLANケーブルの耐用年数は、自然な劣化を前提にすれば20~30年程度といわれているため、環境によっては数年ほどで劣化してしまう場合もあります。

有線LANのケーブルタイプ
LANケーブルは、規格や形状などが異なるさまざまな種類があります。
ここでは3つの項目ごとに、LANケーブルのタイプを解説します。
カテゴリ
LANケーブルには「カテゴリ」という概念があり、カテゴリが大きいほど伝送速度が速くなっています。

現在主流なのは1000BASE-Tなので、新しく用意する場合はカテゴリ6を準備すれば問題ありません。
なお、カテゴリ5e以前の「カテゴリ5」や「カテゴリ3」を利用している場合は、ギガに対応しないため買い替えをおすすめします。
お使いのケーブルのカテゴリは、コネクタ付近のケーブルに印字されている文字から確認できます。
形状
LANケーブルの形状には主に次の3タイプがあります。

配線する場所に応じて、適切な形状のものを選択しましょう。
シールド保護
LANケーブルは電磁波ノイズに弱いという特性があります。
ノイズを避けることが難しい環境ではシールド保護されたものがおすすめです。

有線LANの導入手順
ここでは、すでに無線LAN(WiFi)がある状況から、一部のデバイスを有線LANで接続する手順を解説します。
デバイスにLANポートがあるか確認
まず、接続させたいデバイスにLANポートがついているか確認しましょう。
最近のノートPCはLANポートなしのものが多くなっています。
LANポートがついていない場合は、デバイスのOSとコネクタの形状に合ったLANアダプタを用意してください。
ルーターや無線APの空きポートを確認
デバイスをつなぐ機器に空きポートがあるか確認しましょう。
現在無線ルーターを利用している場合は、デバイスから無線ルーターに直接つなぐのがおすすめです。
ポートが足りない場合は、ハブやスイッチを準備しましょう。
配線ルートを考える
配線するルートを考え、必要な部材を揃えましょう。
電気信号は機器が発する電磁波や水に弱いため、それらから遠ざけるように配線ルートを考えましょう。
配線ルートが決まると、LANケーブルに必要な長さやケーブルの形状、モールの本数が決まります。
配線作業を行う
部材を揃えたら配線作業を行い、デバイスと無線ルーターを接続しましょう。
LANケーブルは基本的に接続するだけで通信できるようになるため、設定は不要です。

有線LANと無線LANの特性を活かした併用がおすすめ
有線LANは配線こそ面倒ですが、有線LANを取り入れることで、高速で安定した通信環境を実現できます。
有線LANと無線LANそれぞれの特性を活かし、端末に応じて併用するのがおすすめです。
 固定IPアドレスとは?活用シーンとメリット・デメリットをわかりやすく解説!
固定IPアドレスとは?活用シーンとメリット・デメリットをわかりやすく解説!
2023-9-20
 DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?基礎知識や進め方、成功事例を解説!
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?基礎知識や進め方、成功事例を解説!
2023-5-16
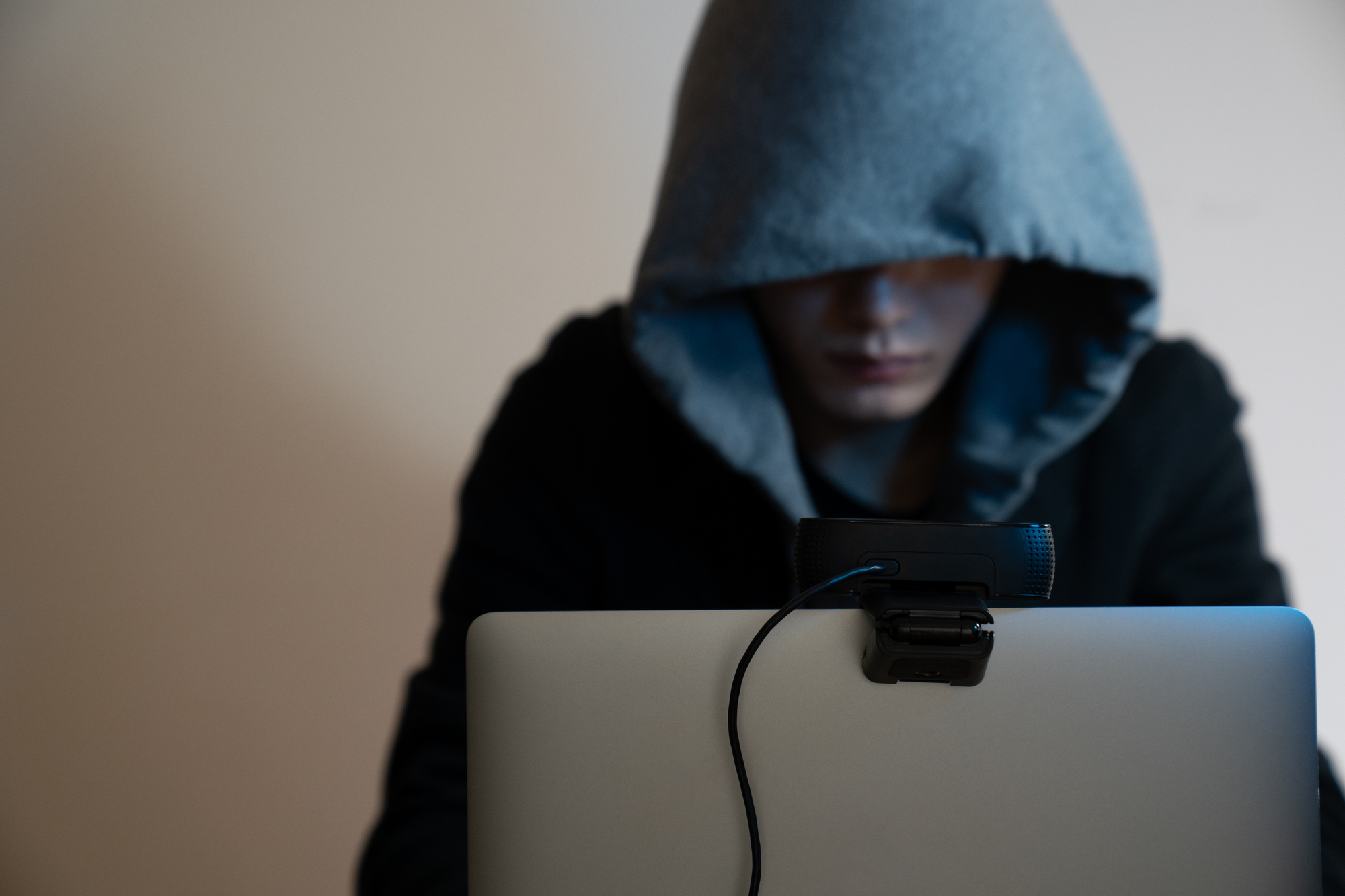 サイバー攻撃とは?種類と企業に必要な対策をわかりやすく解説!
サイバー攻撃とは?種類と企業に必要な対策をわかりやすく解説!
2024-4-24
-
# U3# ガイドライン# LOOOK# ローカル5G# PBX# doracoon# イントラネット# PBXとは# DoRACOON# WiFi# DOR02# ゼロトラスト# デジタルサイネージ# 周波数帯# クラウドPBX# イントラネットとは# BCP対策# セキュリティ# 電源入らない# VPN
 急にインターネットが遅くなる11の原因と対処法
急にインターネットが遅くなる11の原因と対処法
2023-07-12
 快適にインターネットを利用できる回線速度の目安は?速度が遅い時の改善方法も解説
快適にインターネットを利用できる回線速度の目安は?速度が遅い時の改善方法も解説
2023-06-26
 【徹底解説】5Gの周波数帯「ミリ波」・「Sub6」・「4G周波数帯の転用」について
【徹底解説】5Gの周波数帯「ミリ波」・「Sub6」・「4G周波数帯の転用」について
2024-03-18