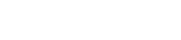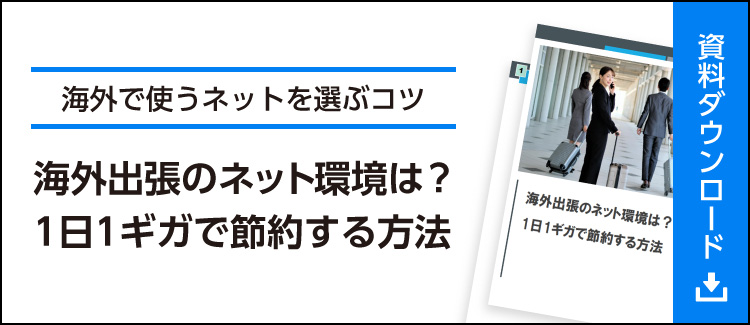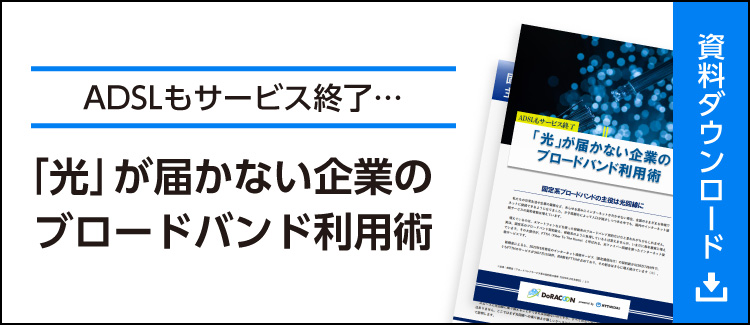2020年3月から免許交付が開始されたローカル5Gとは、地域のニーズや個別のニーズに応じて、柔軟に構築できる無線通信システムのことです。
DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する企業において、ぜひ抑えておきたいキーワードです。
本記事では、ローカル5Gの概要やキャリア5G・プライベート5Gとの違い、メリット・デメリットについてわかりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。
INDEX
ローカル5Gとは
ローカル5Gは、地域(ローカル)ニーズや個別のニーズに応じて、さまざまな主体が柔軟に構築可能な無線通信システムです。無線通信に、5G(第5世代移動通信システム)を使うことが特徴です。
全国にエリア展開する移動体通信事業者(キャリア)からも5Gが提供されており、それらと並行する形でローカル5Gが展開されます。

ローカル5Gを構築するときは、無線免許を取得し、無線通信するための設備を準備する必要があります。
キャリア5Gとの違い
キャリア5Gとは、NTTドコモやau、ソフトバンク等のキャリアが展開する5Gサービスです。
ユーザーはそれぞれのキャリアと契約することで、5G回線を使ってインターネット接続できます。
一方ローカル5Gは、ユーザー自身で設備を設置し、運営する自前の5Gです。
社内ネットワークの構築に無線LAN(WiFi)を利用するケースで例えると、「ローカル5Gは無線LANの代わりとして利用するもの」と考えるとわかりやすいかもしれません。
プライベート5Gとの違い
プライベート5Gとは、ソフトバンクが法人向けに提供するサービスの名称です。
キャリア5G網を仮想的に分離し、その分離した5Gネットワークを法人の無線ネットワークとして提供するものです。
5G設備は既存の無線基地局を利用し、ソフトバンクユーザーと共用します。
仮想的に分離する技術として「ネットワークスライシング」が使われています。
スライスされたネットワーク同士は互いに独立しており、特定のスライスで生じたトラブルや通信障害は、他のスライスに影響を及ぼしません。
ローカル5Gとは異なり、免許取得や設備の構築・運用が不要です。
ローカル5Gの特徴・メリット
ローカル5Gを使うメリットについて解説します。
ネットワークを柔軟に構築できる
キャリア5G(パブリック5G)と比べたときのローカル5Gのメリットは、個別ニーズに応じて柔軟なネットワーク設計ができることです。
たとえば超高精細な映像を送付する業務が多い場合は、下りよりも上りを優先することが可能です。
また利用するデバイスが多いエリアには無線基地局を多めに設置するなど、基地局の設置場所についても柔軟に対応できます。
セキュリティ対策になる
ローカル5Gは機密性が高く、セキュアに通信できます。理由は次の2つです。
・自社が専有する回線だから
・ユーザー認証をSIMカードで行うから
キャリアが展開する5Gは自社だけでなく、一般の人も使う公衆回線です。自社のみが利用するローカル5Gのほうが、安全性の高い通信が行えます。
またローカル5Gでは、ユーザーの認証をSIMカードで行います。対応したSIMカードが入っていない端末は、基本的にローカル5G網にアクセスできません。
ID・パスワードや電子証明書でユーザーを認証するWiFiよりも、セキュアな無線通信環境を構築できます。
またローカル5Gでは、ユーザーの認証をSIMカードで行います。対応したSIMカードが入っていない端末は、基本的にローカル5G網にアクセスできません。

通信障害の影響を受けない
ローカル5Gは、キャリア5Gとは別のネットワークであるため、キャリア側で通信障害があっても、影響を受けにくいしくみです。
また無線基地局は自社が許可している人だけがアクセスできるシステムなので、そもそも混雑しにくいといえます。
ローカル5Gのデメリット
ローカル5Gのデメリットについて解説します。
無線免許の取得が必要
5Gを利用するためには無線免許を取得する必要があります。
企業の無線ネットワークとして一般的に使われているWiFiは、総務省の定める「免許を要しない無線局」の条件を満たしているため、免許が不要です。一方、5Gは「免許を要しない無線局」に該当しないため、総務省へ届け出て免許を取得する必要があります。
WiFiでは、機器を買ってセットアップすればすぐに無線を利用できます。一方ローカル5Gでは、上記のステップを踏まないと利用できません。WiFiに比べるとかなり面倒なことがおわかりいただけると思います。
また免許を取得後、無線設備や設置場所を変更する場合は、再度総務省に対し届け出や申請が必要です。
コストが莫大にかかる
WiFiを構築するのに必要なものは「無線アクセスポイント」です。価格は1万円弱のものからあり、高くても20万円程度(参考 価格.com)です。
設置する環境や接続台数等によって用意する機種や台数は異なりますが、構築する費用が超高額になるケースは少ないでしょう。

一方ローカル5Gの構築に必要なものは、「無線基地局」と「データ処理を担う設備(コアネットワーク)」です。
無線基地局はWiFiでいうアクセスポイントのことで、デバイスと無線通信する機能を持つものです。
コアネットワークはデータの処理を行うシステム部分であり、無線基地局から有線で接続されます。オンプレミスで構築するパターンと、クラウドで利用するパターンがあります。
無線基地局とコアネットワークを含めたシステム全体の導入費用としては、約500万~数千万円程度かかるようです。(下記記事を参照)
”NECが一体型基地局でローカル5Gを価格破壊、498万円から
NECは2022年1月20日、ローカル5G向けの新たな基地局「UNIVERGE RV1000シリーズ」の2機種を発表した(図1)。最大の特徴は、基地局構成をシンプル化し、これまでシステム全体の導入費用が数千万円かかることが一般的だったローカル5Gの価格を、500万円以下から利用できるようにした点だ。”
引用:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/12076/
WiFiに比べるとかなり高額になることがおわかりいただけると思います。
ローカル5Gの導入方法
ローカル5Gを導入する方法について解説します。
設備の準備
ローカル5Gを導入するには、5G無線設備を自前で準備する必要があります。
準備するもの大きく分けると、以下の2つがあります。
- ・無線基地局
- ・5Gコア
無線基地局は、製品ごとに利用できる周波数が異なっています。

高精細な画像を送信する用途ならミリ波対応、LANの代わりとしての利用ならSub6など、利用用途に合わせて周波数を選択し、適切な製品を選んでください。
2つ目の5Gコアは、5Gネットワークの中心となるシステムです。
ローカル5G導入当初で主流だったのは、コア部分を4G用のシステムとし、一部のみを5G対応にしたNSA(ノン・スタンドアローン・システム)です。
ただNSAは5G回線と4G回線の両方を利用できるものの、コア部分が旧システムのため、5G本来の性能は発揮できません。
2022年以降は5G回線のみに対応するSA(スタンドアローン)方式の運用が本格化し、SA方式の製品が増加しています。
免許申請
ローカル5Gの運用には、無線局の免許申請が必要です。
免許は利用する企業の社員が取得する方法と、5Gシステムを構築するシステムベンダーによって取得してもらう方法があります。
免許取得までは次の4ステップです。
1.書類を揃えて申請
2.審査後、予備免許交付
3.落成検査を受ける
4.免許交付
ステップ1で必要となる書類は、申請書と、「無線局の開設目的、設置場所、使用する無線機の工事設計など」を記載した添付資料です。
書類作成に時間がかかるので、余裕をもった手続きが必要です。
ローカル5Gで何が実現できるのか
ローカル5Gがもたらすメリットは、基本的にキャリア5Gと同じです。つまり「高速大容量・低遅延・多接続」です。
では「高速大容量・低遅延・多接続」は、どんなことに役立つのでしょうか。
高速大容量は、高精細画像を瞬時に送ることに役立ちます。低遅延は、ロボットの制御などクリティカルな操作が必要なものに役立つでしょう。多接続は、多数のセンサーが同時にネットワーク接続するのを手助けします。
ローカル5Gは、これらの機能を活かせるアプリケーションの基盤となります。アプリケーションの導入により、企業が抱えているさまざまな課題を解決できるでしょう。
たとえば製造業においては、次のようなことに活用できます。
・目視作業の自動化
・遠隔操作支援
なお農業やエンターテイメント、医療等の分野においても、ローカル5Gの特徴を活かしたサービスの展開が期待されています。
目視作業の自動化
高精細画像データとAI解析を用いて、これまで人が行っていた目視作業を自動化できます。製品の目視作業を自動化することで、より少ない人数で同じ業務をこなしていけるようになり、人手不足が解消されるでしょう。
遠隔操作支援
高精細映像をリアルタイムに伝送することにより、遠隔にいる熟練者から支援を受けられるようになります。
熟練技術者が現場にいなくても、現場にいるのと同様の支援を受けられるようになるでしょう。熟練技術者の不足による対応の遅れが解消されます。

まとめ
ローカル5Gを活用すると、自社専用の5Gネットワークを柔軟に構築できます。一方で「無線免許の取得が必要」・「高額な設備投資費がかかる」など、ローカル5G導入までのハードルは非常に高いといえるでしょう。
 固定IPアドレスとは?活用シーンとメリット・デメリットをわかりやすく解説!
固定IPアドレスとは?活用シーンとメリット・デメリットをわかりやすく解説!
2023-9-20
 DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?基礎知識や進め方、成功事例を解説!
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?基礎知識や進め方、成功事例を解説!
2023-5-16
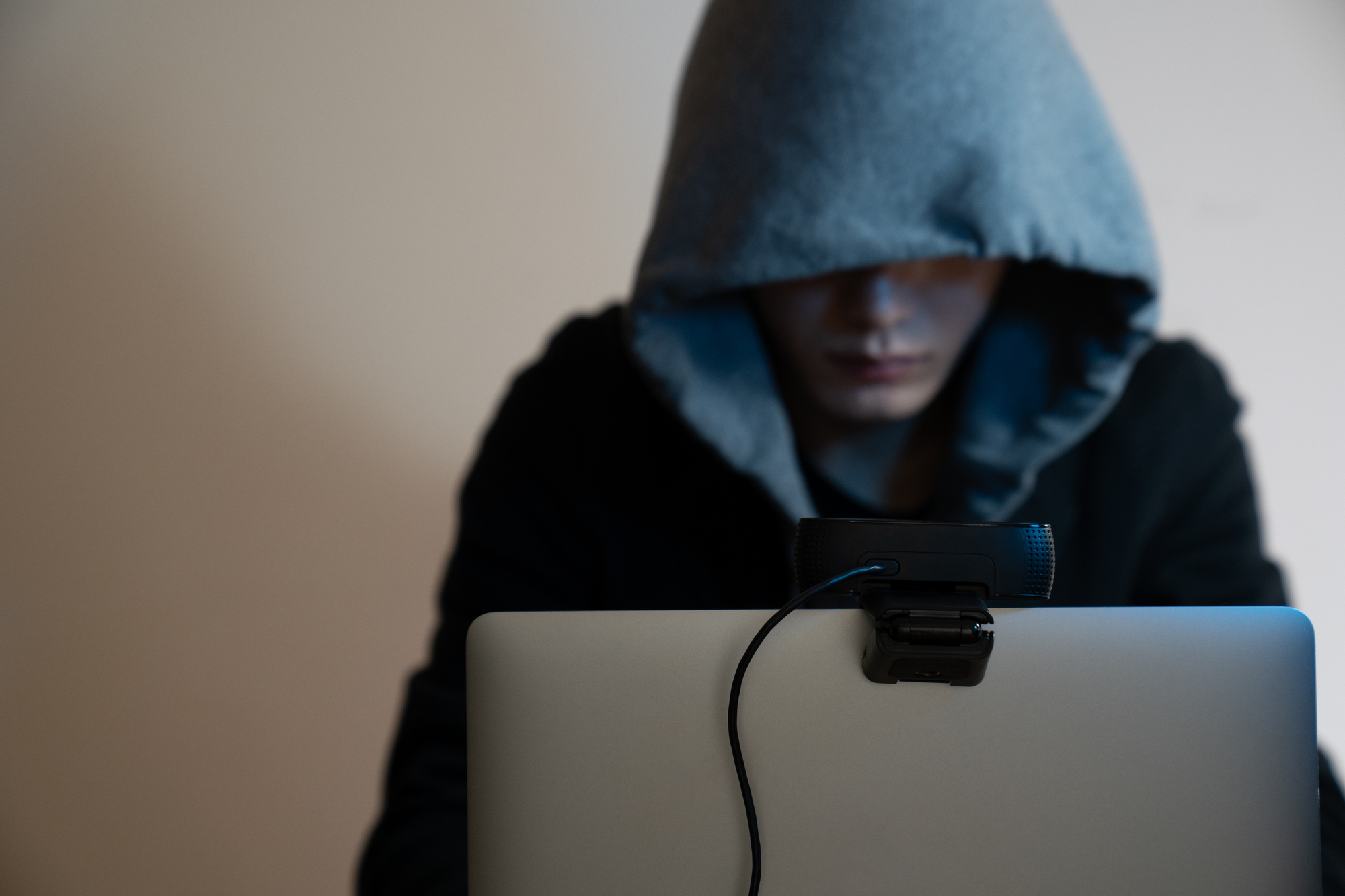 サイバー攻撃とは?種類と企業に必要な対策をわかりやすく解説!
サイバー攻撃とは?種類と企業に必要な対策をわかりやすく解説!
2024-4-24
-
# リモートワーク# 解説# 原因# GIGAスクール# ネットワークセキュリティー# 育児休業法# YT40# ポケット型WiFi# ICTツール# エモテット# 事業継続力強化計画# セキュリティ対策# モバイルルター# YT65# 海外出張# インボイス# VPN仕組み# ADSL終了# Emotet# インターネットVPNとIP-VPNの違い
 急にインターネットが遅くなる11の原因と対処法
急にインターネットが遅くなる11の原因と対処法
2023-07-12
 快適にインターネットを利用できる回線速度の目安は?速度が遅い時の改善方法も解説
快適にインターネットを利用できる回線速度の目安は?速度が遅い時の改善方法も解説
2023-06-26
 【徹底解説】5Gの周波数帯「ミリ波」・「Sub6」・「4G周波数帯の転用」について
【徹底解説】5Gの周波数帯「ミリ波」・「Sub6」・「4G周波数帯の転用」について
2024-03-18